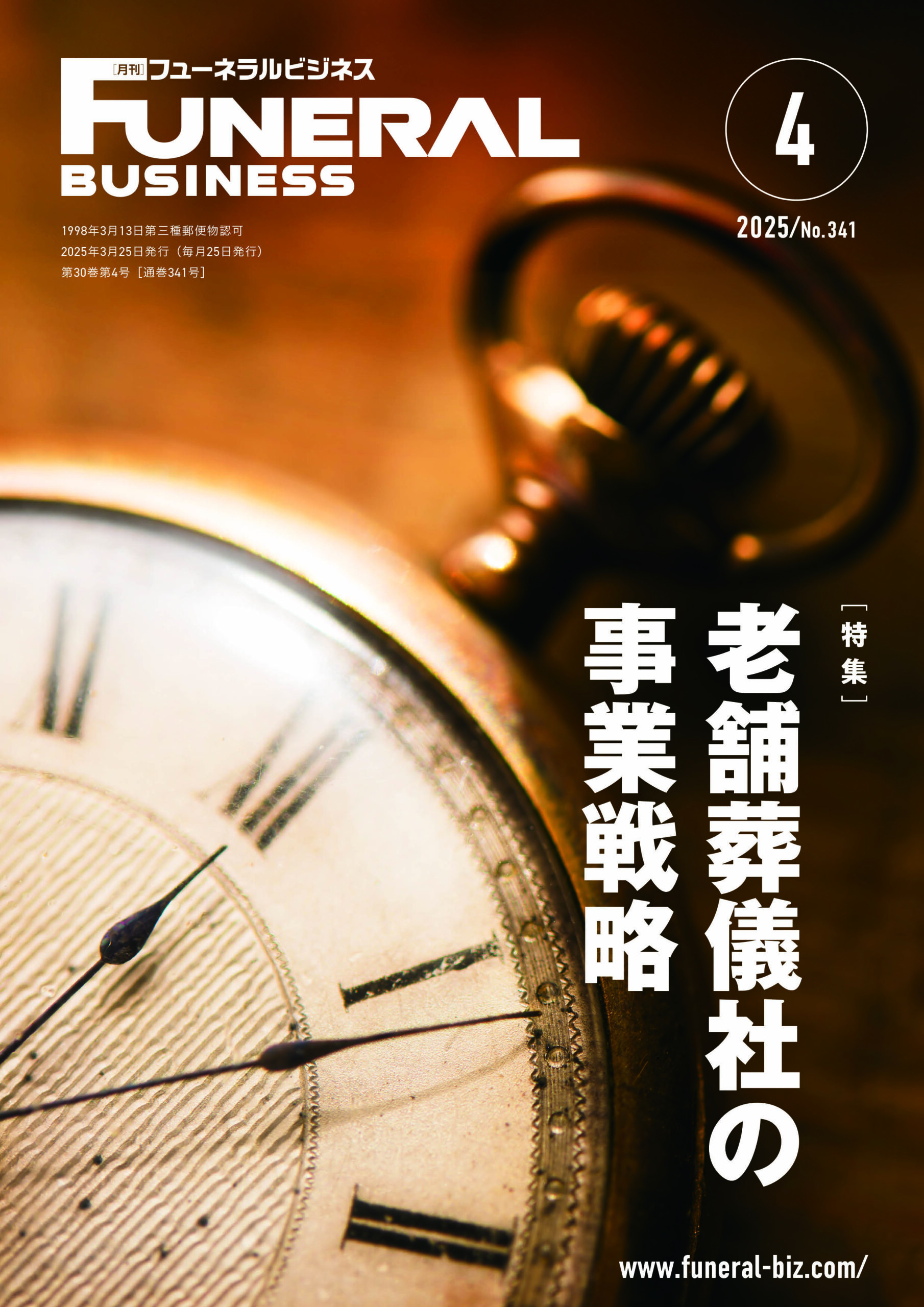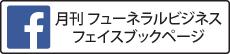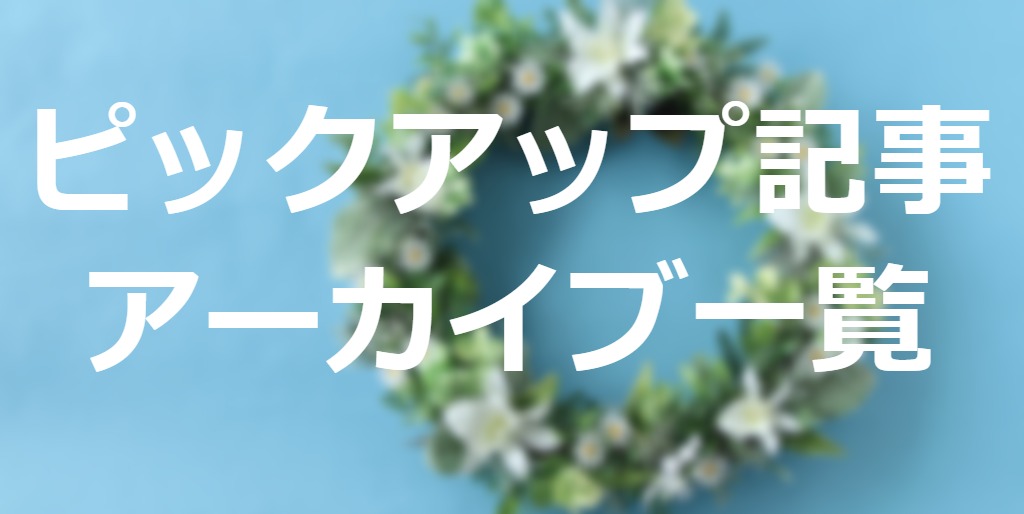――花安[新潟県新発田市]
事業多角化で雇用と安心生み出し
地域経済の活性化目指す
[特集]老舗葬儀社の事業戦略 ケーススタディ
新潟県新発田市を拠点に葬祭事業等を展開する㈱花安。同社に残る史実を辿ると、その創業は江戸文政期の1812年、初代・花屋安兵衛が新発田藩主から藩御用達の花屋のお墨付きを受けたときからはじまったとされている。その後、造花職人として「花屋安兵衛」を営むなかで、葬儀花も提供していたこともあり、葬儀との関わりは第2次世界大戦前からはじまっている。葬祭業に本格参入したのは、十四代社長渡邊安介氏のときに「花安葬儀店」を開業した戦後間もない頃。1987年に第1号会館を開業し、新発田市を中心に葬祭事業の基盤整備に着手する。その後、多角経営に乗り出し、2024年には新潟市へ進出を果たすなど、昨今、精力的な動きをみせる同社代表取締役渡邊安之氏に話を伺った。
「家族葬ショック」を機に
家業から企業への脱却目指す
十六代目社長である渡邊安之氏が家業に戻ったのは2011年のこと。同社における本格的な葬祭事業の礎を築き上げた十五代社長である渡邊克美氏(当時社長/現会長)から、創業からの歴史を聞く機会が多かったことから、「家業を潰してはならぬ」との思いに駆り立たれ、教職を辞して家業に戻った。
とはいえ、当時は会葬者が100人以上という一般葬(二日葬)隆盛の頃ゆえ、経営基盤を整備するというよりも、受注した葬儀施行を“こなす”ことで精いっぱいだったという。「それゆえ、会社経営という概念は整備されておらず、葬祭業という家業が、ただ単に大きくなっていったという感じでした」と渡邊社長。そうしたなかで、経営的な危機感をもちはじめたのが、13~14年にかけて新潟県内で生じた「家族葬ショック」だった。
「その数年前から会葬規模が徐々に減少したこともあり、本館横に家族葬向けの小規模会館を開業したのですが、結果として施行単価も下がってしまった」と、業界全体の流れが小規模葬へと移行するなか、何はともあれ小規模会館の開設を急いだために、提供する商品プランのことを置き去りにした結果、単価低下が起こったと後に理解する。
ただ単に時流に乗った開発を先行したとしても、そこで提供するサービスや商品プラン設計等を含めて両輪で検討しないことには、はじまらない。「施行件数は伸びたとしても売上高が減少してしまってはまったく意味がない。そこで、ふと気づいたのが、将来的な企業成長のビジョンを描くことだったのです」と渡邊社長が語るように、この経験をもとに、「家業から企業」へと成長戦略を描くことに奔走することになる。
地元観光施設の運営受託を機に
地域経済とのネットワークを拡大

組織改革を進めるなか、単なる葬祭事業者としての取組みだけでは「花安の将来ビジョンを描くことは不可能」と判断した渡邊社長(当時は常務職)は、地域を巻き込むイベントを仕掛ける。
そのきっかけが、2019年から新発田市から受託した「寺町たまり駅」の観光施設運営だった。寺町たまり駅とは、新発田城の城下町が整備された際、寺を一角に集めた「寺町どおり」に位置する市の観光拠点。その指定管理者として同社が運営を受託、営業を開始したもので、その寺町どおりでは、花安が運営母体になり15年から「しばた寺びらき」(以下、寺びらき)なるイベントが開催されていた(コロナ禍中は休止)。
地域経済との密接な関わりのきっかけとなった観光施設「寺町たまり駅」
同社では、寺町たまり駅の受託を機に寺びらきのイベントに以前にもまして積極的に関わるようになり、同イベントに参画する寺院や商店街の店主らと親交を深めていく。こうした「異業種との連携」から、渡邊社長は、新発田市で葬祭事業を展開する花安ならではの“地域密着”とは、地域住民とのつきあいだけにとどまらず、地元経済を支えるこうした商店主らとの連携も不可欠であることを痛感。「死亡人口や生産人口がピークアウトへと向かうなか、町(地域)の衰退はすなわち花安の事業存続に関わる。そうであるなら、地域経済を復活させることが、結果として花安の事業存続の道である」と、葬祭業に固執せず、地域経済の復興に向けた異業種連携に着目するようになった。
こうしたなかで誕生したのが、市内の温泉郷・月岡温泉の街中にあるクラフトビール「月岡ブルワリー」だ。月岡ブルワリーは、同店の醸造責任者である新保典司氏が、「日本酒が大好きで、いつか全部自分でつくってみたいと思ったこと」がきっかけだった。
新保氏は新発田市内で「新保酒店」を営む三代目で、寺びらきのイベントの際、寺町たまり駅と共同で寺のイメージに掛けて「大仏ビール」(湘南のクラフトビール)を販売したことを機に、渡邊社長らと意気投合。クラフトビールの人気の高さを、衰退する新発田市の起爆剤とすべく、“月岡温泉という「観光地」×気軽に楽しむことができる「レストラン併設」×小規模な「マイクロブルワリー」”をコンセプトとする醸造所を月岡温泉の街中に設立しようと、20年9月1日にクラウドファンディングを実施。予想を上回る支援金(308万5,000円)を集め、同年11月に開業している。
開業後、その味は多くの愛飲家に支持され、翌21年9月に開催された「International Beer Cap2021」にて、《月岡湯上りペールエール》が銀賞を受賞。醸造開始後、1年にも満たないクラフトビール醸造所が国際大会で受賞するのは稀で、その商品力の強さがまさに本物であると証明されたといえる。
20年といえば、まさにコロナ禍の只中にあった時期で、当時、政府は“不要不急の外出はしないように……”との方針を打ち出したのも記憶に新しい。そんななか、月岡ブルワリーが、葬儀の小規模化にさらに拍車がかかった状況下で同社の売上げを支えたことはいうまでもない。


月岡温泉の街中に開業した「月岡ブルワリー&キッチンGeppo」外観(左)。月岡ブルワリー内観(右)。奥に見えるのがクラフトビール醸造スペース
花安では、2020年には樹木葬墓地を開園したほか、25年からは不動産事業に参入するなど、多角経営化を推進している。全編は『月刊フューネラルビジネス2025年4月号』でお読みいただけます。
また、花安の渡邊社長は、6月4日(水)・5日(木)に開催される「フューネラルビジネスフェア2025」のシンポジウムにも登壇予定。「世代交代を機に”攻めの営業”を展開し飛躍――その事業戦略と次代を担う同世代への助言」と題したリレー講演で語っていただきます。