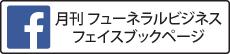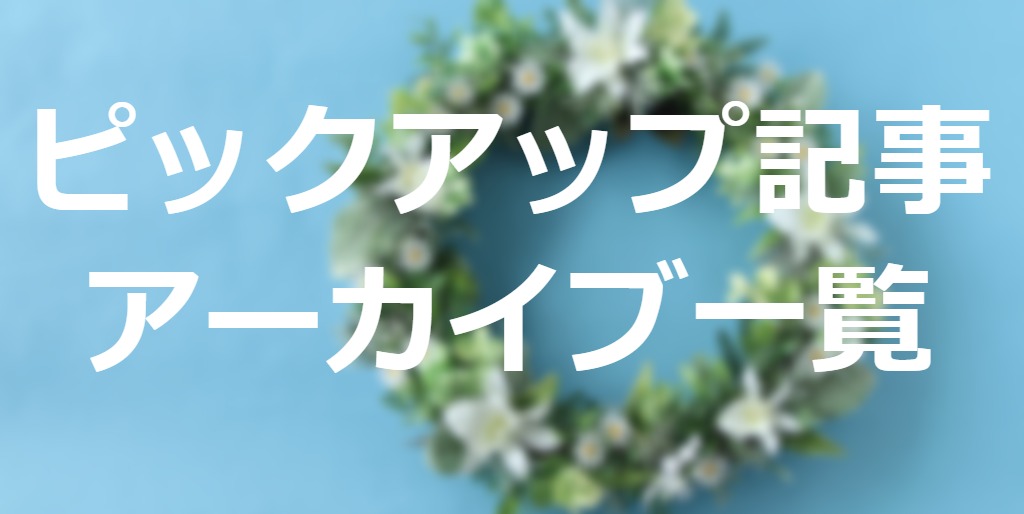[インタビュー]㈱ティア 代表取締役社長 冨安徳久氏

東証スタンダード/名証プレミア上場企業であり、中部・関西・関東に直営、FC等を含めて200会館以上を展開する大手葬儀社の㈱ティア(本社名古屋市北区)は、2023年11月、㈱八光殿(本社大阪府八尾市)、㈱東海典礼(本社愛知県豊川市)および関連会社をグループ化。M&Aを成長戦略の柱の1つとして具現化した。そのM&Aに対する考え方、今回のグループ化の経緯や効果、今後の展開などについて、創業者である代表取締役社長の冨安徳久氏に伺った。
直営・FC・M&A・企業連合が成長戦略の4本柱
――はじめに、貴社におけるM&Aの位置づけについてお聞かせいただけますか。
冨安 1997年にティアを設立したときから全国制覇を掲げ、「日本で一番『ありがとう』と言われる葬儀社」であるティアの葬儀を47都道府県に届けることを目指してきました。名古屋からスタートして東海・中部地方、そして関西・関東と、基本的に直営会館を開設してエリアを広げてきました。さらに教育システムが整備できたらFCへの着手を考えておりましたので、2006年からFC展開を開始しました。
M&Aによるエリア拡大も、東京-名古屋-大阪という太平洋ベルトを中心に考えていたのですが、なかなか成立に至りませんでした。ここ数年、候補にあがった会社もいくつかありますが、調査をしてみるとさまざまな問題があり投資案件ではないと判断したり、デューデリジェンス(企業価値評価)までかけたのに成立しなかったりということが結構ありました。
現在、ティアが全国制覇をするための柱は4つあります。1つ目が直営、2つ目がFC、3つ目が今回のテーマでもあるM&A、そして4つ目が同業他社の経営が立ち行かなくなったときに、再教育で当社のノウハウを取り入れてもらい、葬祭業務をリブランドしてティアブランドとして任せていくという企業連合のような形です。なかでもM&Aは、全国制覇するためのエッジとなる戦略だと考えています。
いまはM&Aの時代。あらゆる業種・業態において、立ち行かなくなった会社の救済や事業承継などの意味でM&Aの重要性は増しています。葬祭業でも、現在の葬儀単価では明らかに事業活動ができなくなる会社もありますので、M&Aは重要なファクターになってきています。今後については、直営・FCとも各事業部で注力していきますが、やはりM&Aにいちばん注力するべきと考えています。そこで数年前から社内にM&A推進室を立ち上げ、全国に対象となる会社があるかどうかを徹底的に調査しながら進めているところです。
――2023年11月に、M&Aで八光殿と東海典礼および関連会社をグループ化されました。その経緯と狙いについて教えてください。
冨安 私どものM&A戦略上、まずは地元を固めようと、中部地方でのM&Aの対象になり得る会社を自社で徹底的に調べ上げたのです。その結果、東海典礼となりました。それで東海典礼の詳細を確認したところ、すでに日系投資ファンドのNSSK(㈱日本産業推進機構)に買収されていました。
ファンドに買われたということは、資本が移動していることになります。また、ファンド側は、絶対どこかでイグジット(出口戦略)を考えます。ファンドが東海典礼の株式を手放す際は、売却の話を真っ先にしてもらえるように、先行してファンドに訪問し、声をかけてもらえるような2社の関係性を構築しました。売却に関する話が出るまで数年はかかると予測していましたが、1年も経たないうちにファンド側から話がありました。「これは願ってもないことだ」と思って先方にお会いしたところ、「実は売却を考えている企業がもう1社ある」ということで、ここではじめて八光殿の話が出てきました。調べてみたら、八光殿も素晴らしい会社でしたので、2社同時に譲り受ける運びとなりました。
当社にとっては大きな投資となりますが、決断のポイントはエリア戦略が1つ目です。東海典礼は愛知県東部の東三河地域を中心に22会館を、八光殿は大阪府八尾市を中心に16会館を運営しており、両社ともに当社が出店していないエリアをパズルのピースを埋めるようにカバーする案件だったのです。当社がグループ化すれば最も大きなシナジー効果が出せると考えました。特に東海典礼が主要商圏とする東三河地域には豊川市をはじめ蒲郡市、新城市があり、このエリアを他社に押さえられてしまうと戦略的に大きな痛手です。
もう1つのポイントは、両社ともにそれぞれの地域に根差した事業展開を通じて、安定した基盤を築いてきた葬儀社であるということです。そのため、グループ化した後の成長戦略を描くことが可能だと判断しました。1+2=3ではなく、4にも5にも6にもしていかなければ意味がないというのが、私どものM&Aの考え方です。
買収された側/した側ではなく、同じ志をもつ同士・仲間という意識
――2社のM&A後1年が経過しましたが、貴社の葬儀スタイルや理念の浸透などについてはいかがでしょうか。
冨安 PMI(M&A成立後の経営統合を行なうプロセス)を進めていくなかでまず苦心したのは、財務経理の統合でした。1社ではなく2社、しかも両社とも未上場企業なので、前月の数字を出すこと1つとってもスピードが遅い。これを上場企業の基準に合わせなければなりません。財務経理に関しては、当社の財務本部を中心に顧問税理士と協力して取り組み、第2四半期の決算から連結で発表できるようになりました。
業務の統合は、もちろんそれぞれの企業風土もありますが、同じ葬祭業で「お客様にありがとうと言っていただける」という想いが共有できていますのでスムーズに進んでいると思います。何より「人がすべて」だということ、人や教育がとても重要であると早期に理解していただいたことが大きいです。私も両社の社員を対象にして社長セミナーを行ないました。
その際、社員と対面する前には動画を撮影し、対象会社に視聴していただきました。その内容は「『買収された側/した側』ではなく、全国制覇するために同じ志をもった同士・仲間を得たと思っているので、ともにご遺族から感謝をいただきながら、全国にこのティアグループの葬儀を届けましょう」といったものです。買収というと負のイメージをもつ人もいます。そうした不安をできるだけ取り除く方法を考えつつ、業務の統合をすすめ、1つひとつ不安や疑問を取り除いていったという感じです。
最後は意識の統合、理念の共有です。私がこれまでに行なってきたさまざまなテーマでの講演やセミナーも動画で見られるようにするなど工夫しています。一挙にとはいきませんが、徐々に意識の統合をしていく、これはあまり焦らないほうがいいと私は思っています。
また、当社のポリシーとして、リブランディングがあげられます。そのエリアで長年にわたり一定のシェアを維持してきた会社には相応の実績があるので、そこはバランスよく、状況に合わせて時間をかけてやらなければと思っています。
インタビュー後半では、「売上げや施行件数など、M&Aのメリット、グループ化によるシナジー」「ティアのM&Aの展望・スタンス」についても伺った。全編は『月刊フューネラルビジネス2025年3月号』でお読みいただけます。