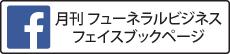――大谷賢博 氏[サンレー(北陸)紫雲閣事業部部長]
被災者、上級グリーフケア士として
遭遇・体験した能登半島地震
[特集]重要性高まる「グリーフケア」|レポート
今年1月1日に起きた「能登半島地震」においては、直接死、関連死を合わせて死亡者が401人(10月1日現在)にのぼり、いまだに避難所生活を余儀なくされている人も多い。
サンレー(北陸)で紫雲閣事業部部長を務める大谷賢博氏は、石川県羽咋郡志賀町にある実家に帰省していたところ、能登半島地震に遭遇。同氏は冠婚葬祭文化振興財団の資格制度である上級グリーフケア士の資格を保有していたことから、現地に残ることを決め、避難所で生活をしながら被災者のグリーフケア活動を実践した。本レポートでは、大谷氏にその体験を語っていただいた。
帰省中に起こった令和6年 能登半島地震
正月に石川県羽咋郡志賀町にある実家に帰省し、久しぶりに両親と弟と一緒に正月番組を見ながらくつろいでいたところ、突然強い揺れが発生しました。しばらくして揺れが収まったので、家族で外へ出ようかと話し合っていた矢先に、今度はさらに強烈な揺れに襲われ、立っていることもできずに玄関の床に這いつくばるのが精いっぱいでした。激しい横揺れと大きな軋み音で、このままでは家が倒壊して下敷きになると思い、何とか弟と一緒に両親を玄関の外まで引きずり出しました。それが最大震度7を観測し、建物倒壊、津波被害による多くの犠牲者が出た「令和6年 能登半島地震」の発生の瞬間でした。
地震後すぐに大津波警報が発令され、近隣の方々と高台にある墓地まで避難。そこで目にしたのはすべて倒壊して重なり合った墓石でした。混乱のなかで近所の人たちとこれからどうするかを話し合っているうちに夜になり、気温も下がってきたので、今度は皆で車に乗り合わせて国道沿いの山に移動しました。そのときに見上げた夜空にはいままで見たこともないきれいな星空が輝いており、「神様のいたずらではないか」と思いました。


倒壊して重なり合った墓石
車中で過ごしながら考えたことは、「いまここにいる自分の役割とは何か?」ということでした。地震発生後すぐに、弊社社長(サンレーグループ佐久間庸和代表)から安否確認があり、無事であることを伝えると「いくらでも会社を休んで、皆さんの命と心を守ってあげてください!」という言葉をもらいました。私はその言葉で被災地にとどまる覚悟のスイッチが入ったように思います。両親や地域の高齢者の不安感情にどのように寄り添うか、そしてあの状況のなかでも自分自身の「感情プロセスの観察」として感情メモを記録していたことは、上級グリーフケア士として訓練を受けていたからだと後になって気づきました。
グリーフケア士とは、一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団の資格制度です。私はグリーフケア資格研修ファシリテーター養成課程を受講し、2022年4月に上級グリーフケア士の資格を取得しておりました。
避難生活で実感した“供養” は人間の本能

地震発生から一夜明けてから津波警報が解除されました。私は被災者ではありますが、上級グリーフケア士としての活動をすべきと考え、自宅近辺に戻り、世帯ごとの安否確認を行ないました。まだ余震が続いているため建物に入るのは危険と判断し、まずは駐車場で椅子やストーブを並べて簡易避難所として過ごしました。その後、地域の集会所が安全であることを確認し、そこを自主避難所として開設することにし、何とか高齢者を建物の中に入れることができました。そうすると自分の心にも余裕ができ、小さな崖崩れの発生箇所を補修したり、バケツに雨水を溜めて生活用水の確保をし、室内にアンテナ配線でテレビを設置するなど、少しでも皆の心が落ち着ける環境整備に取り組みました。
避難生活でのグリーフケア活動としては、感情プロセスを知ることが重要な要素でしたが、それは葬儀に従事する者がご遺族の感情プロセスを知ることと同じであると思いました。地震発生から数日後に、壊れた自分の家の中で立ち尽くす父親の横に、私も無言で立ち尽くすしかなかったこと、毎日夢を見ているような感覚に陥り、ときにはこの現実を認めたくないという否認、そして、自分の心を最も多く支配した「神に対する怒り」など、自分ではまったくコントロールできない強烈な怒りを人生ではじめて経験しました。
また、空き巣被害、偽自衛官、悪徳工事業者、偽ボランティアによるデマや実際の被害報告が耳に入ってきて、人々が混乱に陥りパニックになっていく様子、さらには震災から1週間経って、皆があまり喋らなくなる抑うつ症状になりました。道路が復旧し両親と一緒に必要物資の買い物や大型銭湯に長時間かけて行った際に、被災していない人たちの笑顔を見て「ここは被災者が来る場所ではない」という疎外感。上級グリーフケア士として被災者の心のケアを行ないたいという思いはあるものの、私自身が実は身も心も疲れ切っていることに気づく瞬間もたくさんありました。
そんな状態のなかでも、自分が回復しグリーフケア活動を実践していくきっかけが、昨年1月10日に亡くなった祖母の一周忌法要でした。当初は、地震により法要をキャンセルしておりましたが、命日が近づくにつれて「何とかお参りだけでもできないか」という思いが強く損壊が少なかった玄関の下駄箱の上に仏具と法名を置いて、住職にお経をあげてもらいました。「供養をする」という行為によって心が安らいでいく感情の流れに、まさに「“供養”は人間の本能」だと気づかされ、それと同時に、被災地には「祈る場所」が必要であるということも実感しました。
グリーフケア士として被災者の心境を傾聴

さらに私を奮い立たせたのは、支援物資の運搬や給水、道路補修や各避難所のパトロール、仮設入浴場の設置を行なってくれた自衛隊員や、警察、消防、DディーパットPAT(災害派遣精神科医療チーム)、JジェイマットMAT(日本医師会災害医療チーム)、日本赤十字社などの各方面のスペシャリストの存在でした。特にDPATが避難所に訪問して、避難者に1人ずつ声をかけ傾聴していく姿を見て激しく心が揺さぶられました。それによって自分自身の辛さや苦しみ以上に、「悲しみを抱えた方に寄り添う」という力がいただけました。
そのときから被災者の感情の動きに敏感になっていったように思います。たとえば安否不明者がまだ323人もいるのに、新聞の地震記事に「復興」や「再建」という言葉がふえてきたことに怒りを覚える人たち。生まれ育った家の一部や、大切な思い出のある品を「瓦礫」や「災害ゴミ」と呼ばれることに苦しむ人たち。どれだけ憔悴していても、電話の相手には必ず「元気や」と言う人たち。震度7でも損傷しなかった頑丈な自宅にいる人たちが大きな余震が来たときに老朽化した自主避難所に集まってきたときは、人は「安全な建物」よりも「誰かといる安心」を必要としているのだと気づかされました。
(続きは本誌でお読みいただけます)
大谷氏は、6月4日(水)・5日(木)に開催される「フューネラルビジネスフェア2025」のシンポジウムにも登壇予定。「サンレーの『悲縁』をつなぐグリーフケアの取組み」と題し、サンレーの代表取締役社長 佐久間庸和氏、グリーフケア推進室 市原奉人氏とともに語っていただきます。