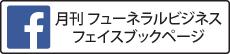――多様化する「遺体安置施設」
存在感増す遺体安置施設
機能と形態の最適化が勝算のカギ
小規模な家族葬会館がスタンダードになったいま、館内に複数の遺体を安置することはむずかしくなった。遺体安置ニーズの高まりや、今後国内の死亡数がふえていくことを鑑みれば、遺体安置施設の整備は特筆すべき必要条件となる。
さらに生活者、事業者双方にとって「ただ安置ができればよい」という認識は古いものであり、プライバシーを確保したうえで費用に見合う空間演出を施し、かつ必要に応じて少人数での直葬や一日葬への対応が可能な遺体安置施設の整備が求められることになる。
そこで今号では、遺体安置室の開発形態別に機能や特徴をクローズアップ。「遺体安置」を取り巻く今日の需要を探る。
自社の事業スキームに最適な
開発形態の選択が不可欠
本誌では、1~2年に一度の頻度で遺体安置施設を特集しているが、今回はできるだけ20年以降に開設した、最新の遺体安置施設をケーススタディに選定。以前の遺体安置施設特集で掲載した事業者にも追加取材を敢行し、遺体安置施設の現状にも迫ることができた。
この取材を通して、各施設を開発形態別に以下のように分類した(図表)。


①既存会館に後付け型(敷地内・別棟)
自社会館の余剰地や駐車場などの一部を利用して新設する。利用者への周知が図りやすいだけでなく、事業者にとっても効率的なオペレーションが実現する。今号ではひない葬儀舎、ホクサンが該当する。
②既存会館に後付け型(建物内)
大型会館などで、現在は使用していない諸室を改装し遺体安置室へ転用する。
③同時オープン型(敷地内・別棟)
新規会館と同一敷地内に整備し、同時開業させる。今号では神保が該当する(同社は①に該当する遺体安置施設も有する)。
④同時オープン型(建物内)
新規会館の建物内に遺体安置機能を組み込む。この場合、葬儀での会葬者とは別の動線を確保することが不可欠となる。今号ではGRATITUDEが該当する。
⑤単独オープン型(複合機能含む)
遺体安置特化施設として開業する。安置機能を集約するため、必然的に遺体の収容数が多い傾向にある。今号ではハース・ジャパンが該当する。
ここで大前提としておきたいことは、各施設の開発パターンはあくまでも概略的な分類であり、営業地域や施行件数、平均施行単価など、各事業者を取り巻く状況はすべて異なる。
遺体の収容数も含めて、どんな開発形態が各社にとって正解となるかはそれぞれで検討し、模索するほかない。既存会館とのオペレーションや開業地の選定なども考慮に入れながら、最も効果的に稼動する施設を目指すことが新たな定石となるだろう。